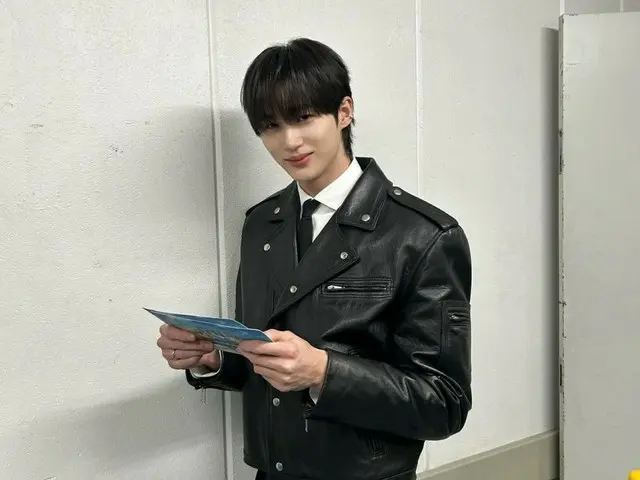『余命10年』監督の藤井道人がプロデュースし、綾野剛主演のドラマ「アバランチ」では藤井と共に演出を担当した新鋭・山口健人監督が現代の日本の若者たちが抱える「病み」を鋭い視点で描く映画『生きててごめんなさい』(通称:イキゴメ)。
この度、完成披露上映会が開催され、主演の黒羽麻璃央、ヒロインの穂志もえか、監督の山口健人、プロデューサーの藤井道人が登壇した。
イベントでは、監督の演出や作品に込めた想い、黒羽が本番が終わってから号泣した話、穂志が、カットがかかった後も、ずっと号泣しながら黒羽に後ろから抱きついていた話など撮影秘話を語った。

冒頭から、黒羽は、「こんなにも早く観て欲しいと思う作品に出会ったのは初めてでした。今日完成披露上映会でみなさまの元に届くことを、非常に嬉しく思っています」、穂志は「自分にとって思い入れのある作品だったということを実感しています。そんな作品をお届けできて嬉しいです」と話し、本作が特別であることを強調。
山口監督は、「お二人の素晴らしいお芝居を皆さまにお届けできる日が来て嬉しいです」、藤井プロデューサーは、「この素晴らしい俳優と山口が力を合わせて作った作品で協働できて光栄です」と、映画の出来に自信を見せた。
企画・プロデュースの藤井は、山口監督について、「インディーズから一緒にやってきて、胆力がすごくある監督。プロデューサーの鈴木さんから『メンヘラの恋愛映画をやりたい』と言われた時に、『俺じゃねえな』と思いました。山口は人を描くのに長けている人間なので、『興味ある?』って聞いたら、自分の恋愛経験も相まってか、食い気味に『やります』と言ってくれたので、お願いしました」と制作の経緯を説明。
山口監督は「『メンヘラ興味ある?』と聞かれて、『メンヘラなら任せろ』って言って」と話し、「そこをもうちょっと広げて、メンヘラだけでなく、現代の若者が抱える葛藤を描ければと思いました」と本作に込めた想いを語った。
黒羽を主演に推薦したのは藤井とのこと。黒羽は、「嬉しいですね。大きな字で書いてください!」とマスコミに呼びかけ、藤井は、「山口も若手というところで、一緒に何かを作ってくれる俳優がいいなと思いました。」と黒羽の起用理由を話した。それを受け、黒羽は、「以前ドラマでご一緒して、『次は映画作れたらいいね』という話を以前からされていたので、その約束を遂に実現できるチャンスでした」と嬉しそうにオファーを受けた理由を話した。
山口監督は、黒羽演じる修一と穂志演じる莉奈について、「修一は僕です。自己投影です。莉奈に関しては、いわゆる『メンヘラ』や『病んでる』という一言で括られちゃうような存在をもうちょっと広げて、どういう思いを持っているのかとか、なんでそういうことになるのかというのを伝えたられたらと思い、描きました」と解説。
黒羽は、修一役について、「割と順撮りに近い感じだったので、日常的な、皆さんがリアルに感じるような、働いている若者の、自分の夢が崩れていくというのを演じ、修一と共に追い詰められているのを実感した日々でした」と撮影中の苦悩を語った。
山口監督は、「(黒羽は、)言いたくないセリフを言わなくてはいけないシーンがあって、黒羽さん本人としては言いたくなかったんですかね。カットがかかったら膝から崩れ落ち、泣いていました」と映画本編には入っていない舞台裏について話し、黒羽は、「殴られたかのようにダウンしました。(自分は)そういう悪口って言えないんだなと思いました。自分でもそんな風になるとは思っていなかったんです。カットがかかって、気持ちを引きずっている自分と、黒羽麻璃央に戻った時の揺らぎみたいなのに襲われました」と、修一を演じたことで予想外の経験をしたそう。

穂志は、オーディションを経て莉奈役にキャスティングされた。莉奈役については、「全部が全部というわけではないんですけれど、『仕方ないよね』と割り切るのが苦手なところは似ているなと思いました。私も『本当にできることはないんか?』となっちゃうようなところがあるし、どこにいても孤独を感じてしまうというところは似ていたかなと思います」と話し、「人間一人一人いろんなものを抱えているので、莉奈に共感できるところはあると思います」と話した。
穂志はカットがかかった後も、ずっと号泣しながら黒羽に後ろから抱きついていたことがあったそうで、「半分莉奈として修一に甘えつつ、黒羽さんとの精神的なコネクションが欲しいシーンだったので、きっと莉奈は普段から修一にこういうふうに抱きついていたんじゃないかと思い、台本には描かれていなかった部分を、物理的に埋めさせていただきました」と、独特のアプローチについて語った。
黒羽は、「最初は『特別になりたい男と普通になりたい女の子』というような設定です。ダメな存在を自分の近くに置いていると自分が楽になるというか、新人の子が近くにいるとホッとするというようなことがあるんですよ。かわいい面もあるし、できないことも可愛いなとどこか自分がホッとするんですけれど、莉奈についてはそう思っていただけでなく、愛おしいなという気持ちも生まれてきた。ただダメだから近くに置いていただけじゃなく、根っこの部分に愛おしさがあった」と演じたことで実際に感じた想いを語った。
山口監督は、「穂志さんのお芝居がとても素晴らしくて、穂志さんは役柄に入り込んでいるタイプなので、カットがかかっても泣いているシーンだとずっと泣いているんです。『OKだよ。よかった』と言いに行こうとすると、僕の書いたセリフを(黒羽に)言われて泣いている穂志さんがいて、『ごめん』っていう気持ちになって」と、撮影中に感じた複雑な心境を語った。
山口監督は、穂志に「莉奈が納得するまで出てこなくていい」と伝えたシーンもあったそうで、「お二人のお芝居の人間性を撮りたかったので、役として実際心が動くまで、そうしなくていいと伝えました」と演出について話すと、黒羽は、「『間をとっても、編集でどうにでもするから、そういう風になるまでセリフを言わなくていいよ』と言ってもらえたので、すごく感謝しております。次のセリフがどうだとか全く考えず、嘘をつかなくてよかったのが、新鮮でもあり、『本当はこうであるべきだよな』と再確認できました」と監督に感謝を述べた。穂志が「本当に結構長いこと出ていかなかったです」と話すと、監督は、「3分くらい出てこなかったんです」と証言し、黒羽は「地獄!」と回想。穂志は、「一つのセリフを色んな言い方にしてくれたりだとかして、乗っている感情が違うなと感じました。許せると思った時に出させていただきました」と裏話を披露した。
本作ではプロデューサーの藤井は、「(僕は)職業として監督をやっているんで、現場でノイズにならないように、1日ちょろっと覗いただけなんですけれど、ラッシュで見て、お二人の芝居がすごかったです。黒羽さんが、途中から山口に見えてきて」と話すと、会場から笑い声が。「穂志さんが化け物みたいにすごくて、役を自分のものにしていた。本作はすごく救いのある映画。ややこしいけれど愛おしい。共感してほしいとか面白いと思って欲しいというのはものづくりの根本としては大事だと思うんですけれど、二人をずっと見守っていたいなと思える、細かい機微がたくさん詰まった宝箱みたいな作品です。『いいお芝居を見せてもらったな』という気持ちです。監督の手腕でもあると思うんですけれど、二人に嘘がない」と3人を絶賛した。
山口は、本作の見どころについて、「登場人物が、そこら辺にいる人というのを意識して描いた作品なので、共感できる部分があれば共感していただいて、共感できない部分があれば、わからないと突き放すのでなく、こういう人間が世の中にいるんだというのも感じとっていただければと思います」と話した。
最後に穂志は、「周りや世間と比べて自分はダメだと思ったり、それを悪いことだと自分を責めてしまう方も、『自分ってこういう人だよな』とダメな部分も含めて丸ごと自分を認めて許せて愛していけるようになるお手伝いをこの映画ができたら嬉しいなと思っています」と莉奈の一番の味方である穂志ならではのメッセージを送った。
続いて黒羽が、「ポスターの『きっと大丈夫。多分。』という言葉が自分の今後の人生の言葉にしたいくらい、すごく好きになりました。補足で『多分。』とつけているあたりに、肩をそっと押してあげているような優しさが溢れていて、この映画を見て、皆さんにも受け取っていただけたらと思います。自分の中で想いのある作品になりましたので、1人でも多くの方に見ていただき、1人でも多くの方に何か刺さるものがあればと思います」と熱いメッセージを送った。
2月3日(金)よりシネ・リーブル池袋、ヒューマントラストシネマ渋谷、アップリンク吉祥寺ほかにて全国順次公開

- ジェイタメ
エンターテインメントはエネルギー。芸能界とファンを応援する芸能情報サイト。
- ジェイタメ